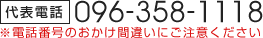5種混合ワクチン
乳幼児が感染すると重症化する恐れのある以下の5つの病気を予防する効果があります。
- ジフテリア:のどの奥に膜ができ、呼吸困難を引き起こす細菌感染症。心筋障害や神経麻痺を合併することもあります。
- 百日せき:激しい咳が特徴の細菌感染症。特に乳児は呼吸ができなくなるなど重篤化し、命に関わることもあります。
- 破傷風: 土の中にいる細菌が傷口から侵入し、神経麻痺や呼吸困難を引き起こす感染症。
- ポリオ(急性灰白髄炎):ポリオウイルスによる感染症で、手足の麻痺や運動障害が後遺症として残ることがあります。日本では現在患者発生はありませんが、海外からの持ち込みを防ぐため接種が重要です。
- Hib感染症(ヒブ感染症):ヘモフィルスインフルエンザ菌b型による感染症で、細菌性髄膜炎や急性喉頭蓋炎など、重篤な病気を引き起こす可能性があります。このワクチンは、1回の接種で複数の病気に対する免疫を獲得できるため、接種回数が減り、お子さんの負担や保護者の通院負担を軽減できるというメリットもあります。多くの人が接種することで、社会全体での感染拡大を防ぐ「集団免疫」の形成にも貢献します。
B型肝炎ワクチン
B型肝炎ウイルス(HBV)への感染を予防します。HBVは肝炎を引き起こし、慢性化すると肝硬変や肝がんへと進行する恐れがあるため、「がんを予防するワクチン」とも言われます。
乳幼児期に3回接種することで、ほぼ全ての子どもがB型肝炎に対する免疫を獲得し、その効果は20年以上持続するとされています。これにより、将来の重篤な肝疾患の発症リスクを大幅に低減できます。
ロタウイルスワクチン
乳幼児の重症なロタウイルス胃腸炎を予防する「飲むワクチン」です。ロタウイルス感染症は、激しい嘔吐や下痢を引き起こし、脱水症状で入院が必要になることもあります。
ワクチンを接種することで、ロタウイルス胃腸炎による入院を約70〜90%減らす効果があり、脳炎などの重い合併症も防げるとされています。現在2種類のワクチンがありますが、どちらも重症化予防効果は同等です。生後早期に接種を開始し、決められた期間内に完了することが重要です。
肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌による感染症を予防します。特に、命に関わることもある細菌性髄膜炎や、重症化しやすい肺炎・菌血症などを防ぐ効果が高いです。現在使用されているワクチンは、多くの種類の肺炎球菌に対応しており、接種することでこれらの重篤な病気の発症や後遺症のリスクを大幅に減らすことができます。定期接種により、乳幼児の健康を守る重要な役割を担っています。
BCGワクチン
結核を予防するためのワクチンです。特に、乳幼児が感染すると重症化しやすい「結核性髄膜炎」や「粟粒(ぞくりゅう)結核」といった重篤な結核に対して高い予防効果があります。
生後1歳までの接種により、小児の結核発症を52~74%程度、重篤な結核を64~78%程度減少させることが報告されています。一度接種すると、約10~15年間効果が持続すると考えられています。日本はまだ結核患者が多い国であり、家庭内感染のリスクもあるため、乳幼児へのBCG接種が推奨されています。
MRワクチン
麻しん(はしか)と風しんを同時に予防する混合ワクチンです。
麻しんは感染力が非常に強く、肺炎や脳炎などの重篤な合併症を引き起こし、時に命に関わることもあります。風しんは発熱や発疹が主な症状ですが、特に妊娠初期の女性が感染すると、赤ちゃんに先天性風しん症候群(心臓病、白内障、難聴など)を引き起こす可能性があります。
MRワクチンを2回接種することで、97%以上の高い確率で免疫を獲得し、これらの病気の発症や重症化を防ぎます。また、社会全体の免疫力を高める「集団免疫」にも貢献します。
水痘ワクチン
水痘帯状疱疹ウイルスによる感染症を予防します。1回の接種で重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回接種すると軽症の水痘も含めてその発症を90%以上防ぐとされています。
発症を完全に防げなくても、ワクチン接種済みの場合は症状が軽く済み、重症化(脳炎、肺炎など)を防ぐ効果が非常に高いです。2014年からの定期接種化により、子どもの水痘発生率が大きく減少しており、医療費の削減にも貢献しています。
おたふくかぜワクチン
ムンプスウイルスによるおたふくかぜの発症を予防します。1回の接種で約80%、2回の接種で95%以上の高い有効率が報告されています。
発症予防だけでなく、おたふくかぜによる重篤な合併症(無菌性髄膜炎、難聴、精巣炎、卵巣炎など)のリスクを大幅に低減する効果が期待できます。特に難聴は後遺症として残ることがあるため、予防接種は非常に重要です。接種率が高まることで、集団免疫が形成され、地域全体での感染拡大を防ぐことにもつながります。
日本脳炎ワクチン
日本脳炎ウイルスによる重篤な脳炎の発症を予防する効果があります。日本脳炎は蚊が媒介する感染症で、発症すると高熱、けいれん、意識障害などを引き起こし、後遺症が残ったり、命に関わることもあります。ワクチン接種により、日本脳炎にかかるリスクを75~95%減らすことができると報告されています。特に小児は重症化しやすいため、適切な時期に接種することで、日本脳炎からお子さんを守り、安心して生活を送れるようになります。
HPVワクチン
小児期のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種は、将来の子宮頸がんやその他HPV関連疾患の予防に非常に効果的です。
HPVは主に性的接触によって感染し、子宮頸がんのほとんどの原因となります。ワクチンは、がんを引き起こしやすい特定の型のHPV感染を予防します。現在日本で定期接種の対象となっている9価ワクチン(シルガード9)は、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐとされています。
特に、性交渉を経験する前の10代前半に接種することで、最も高い予防効果が得られます。これは、ウイルスに感染する前に免疫を獲得できるためです。接種により、子宮頸がんだけでなく、肛門がん、陰茎がん、尖圭コンジローマなどの予防効果も期待できます。
HPVワクチンは、将来の深刻な病気から子どもたちを守る重要な手段として、多くの国で推奨されています。
また、男児がHPVワクチンを接種することで、将来的に男性特有のHPV関連がん(中咽頭がん、肛門がん、陰茎がんなど)や尖圭コンジローマを予防できます。また、パートナーへのHPV感染リスクを減らし、子宮頸がん予防にも貢献します。
3種混合ワクチン
3種混合ワクチン(DPTワクチン)は、ジフテリア、百日せき、破傷風の3つの感染症を予防します。
以下の時期に追加接種(任意接種)が推奨されています
- 就学前(5歳以上7歳未満): 百日せきの抗体は時間とともに低下するため、小学校入学前に3種混合ワクチンの追加接種が推奨されています。これは任意接種となりますが、百日せきに学童期で感染するのを防ぎ、乳幼児への感染源となることを防ぐ目的があります。
- 11~12歳: この時期に接種される2種混合ワクチン(DTワクチン:ジフテリア、破傷風)の代わりに、3種混合ワクチン(DPTワクチン)を接種することも推奨されています(任意接種)。これも百日せきへの免疫を維持するためです。
2種混合ワクチン
主にジフテリアと破傷風の2つの病気を予防するためのワクチンです。
2種混合ワクチンは、主に満11歳以上13歳未満の間に1回接種する「第2期」として位置づけられています。多くの自治体では、小学6年生の時に接種の案内が送られてきます。
ポリオワクチン
不活化ポリオワクチン(IPV)が定期接種として使用されており、主に4種混合ワクチンまたは5種混合ワクチンに含まれて接種されます。
任意接種として推奨されているのは、就学前の追加接種(5~6歳時)です。これは、乳幼児期の定期接種で得られたポリオに対する免疫が時間とともに低下する可能性があるため、小学校入学前に再度接種することで、より長く、高い免疫を維持することを目的としています。この就学前接種は任意のため自己負担となりますが、日本小児科学会も推奨しています。
新型コロナワクチン
- コミナティ筋注(RNAワクチン):接種希望の方は電話で問い合わせください。
渡航ワクチン
(成人から小児まで可能、小児科外来で受け付けます)
- A型肝炎ワクチン:エイムゲン
- B型肝炎ワクチン:ヘプタバックス
- ポリオワクチン:イモバックスポリオ
- 狂犬病ワクチン:ラビピュール
- 日本脳炎ワクチン:ジェービックV
- 髄膜炎菌ワクチン:メンクアッドフィ
- MRワクチン:ミールビック
- 水痘ワクチン:生水痘ワクチン「ビケン」
- 破傷風ワクチン:沈降破傷風トキソイド「生研」
- ダニ媒介性ワクチン:タイコバック
- 腸チフスワクチン:タイフィムブイアイ
その他、抗マラリア薬、高山病予防薬の処方もできます。